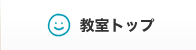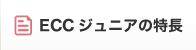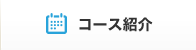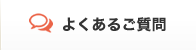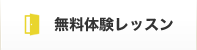2018年10月2日
当教室の生徒さんたちはみなさん、レッスンが終わるとテーブルの上を片付け、わずかな消しゴムの消しカス迄きれいに集めて持参の袋に入れて持ち帰り、テーブルや椅子の位置を戻して退室します。あとから教室を使う生徒さんたちが気持ちよく学習できるようにとの心遣いです。
教室内では当たり前の日常風景ですが、一歩外に出た時このような行動を見かけると、その姿はとても美しく映ります。私は生徒さんたちのこの行動を見る度、誇らしく嬉しく思います。皆さん「美しく生きましょう」。
あるTV番組での「IQの高い学生の全員に共通する分析結果」に興味を惹かれました。
*物心つき始めた幼児に共通する「なに?」「なぜ?」「どうして?」の問いかけに、親御さんたちは無視をしないで一緒に考える時間を設けていた。
*親の学歴、職業、生活習慣には共通点はなかった。
*「疑問を持つこと。調べること」が重要な進化の促進剤。
両親がいないお子さんたちには、出会うすべての人が親代わりであり、その人生に影響することでしょう。良好な環境に恵まれて欲しいものです。スーパーボランティア尾畠春夫さんのように、環境に恵まれていなくても、学ぶことは多そうです。
「それはナゼ?」を大切にすること。「自分で調べること」が老化防止の意外な刺激になる。・・・これ以上の老化を防ぐため、心がけねばと痛感しました。
2018年10月25日
『「お母さんがすき、自分がすき」と言える子に』〈信頼されて子どもは育つ〉
この佐々木正美先生のご著書の第一章は
【最も大切なことは「基本的信頼感」を育てること】
●人を信じる力と自分を信じる力とあります。
子どもは生まれてすぐには、周りの人間に全託し、信じ切って育ちます。特に「お母さん」が大好きです。しかし「自分が大好き」と思って成長している子はどれくらいいるでしょうか?
本書には、《子どもは自分を信じてもらうことによって、信じてくれた人を信じます。そして自分が信じられたことによって、自分を信じることができるのです。》と綴られています。
子どもが心配であれこれ注意したり、こまごまと指示したり、些細なことや親の意に沿わないことに叱ったりということは、子どもを愛しているのではなく、親の望んでいる子どもになって欲しいという気持ちからきていることがある。それは親の「自己愛」である。このような場合、子どもは本当に親に愛されているとは感じられない。云々と続きます。
なるほど、自分の子ども時代を思い出してみて、本当にその通りだなと感じました。
幼い頃はみんな天真爛漫、何をやっても周りから喜ばれ、褒められて育ちますが、だんだん、叱られたり注意されることが増えてくると、自信がなくなり劣等感さえ芽生えてきます。とても自分が大好きとは思えなくなります。
親の愛情がダイレクトに届かなくなるとさまざまな弊害が出てきます。
「自分がすき」と言える子どもに育てるには、どうすればいいのでしょう?
冒頭の「人を信じる力と自分を信じる力」を育てることが大切でしょう。
「子育ては親育て」子どもの成長と同時に親も育ちます。わたしも生徒さんと接する度に元気を貰い、教えを頂いています。
2019年1月1日
新しい年が明けました。みなさんそれぞれ気持ちも新たに、新年の抱負を持たれたことでしょう。
今年こそ、英語を得意科目にしたい。
留学して広く世界の人々と交流したい。
海外旅行で有名なレストランに行き、自由に食事を楽しみたい。等々様々な思いがあることと思います。
2020年には東京オリンピックが開催されます。
いろんな国から多くの人々が来日されることでしょう。外国からの方々が、安心して日本を楽しんで頂けるよう、通じる英会話を習得して、ヘルプできればいいなと思います。
『過去が咲いている今。未来の蕾で一杯な今』
陶芸家 河井寛次郎の言葉です。
人生は「今」の連続である。
「今」を懸命に生きることが過去も未来もよいものにする。
「今」来し方を振り返れば、過去の「今」をどう生きて来たかが見える。
「今」行く末を見通せば、未来の「今」がどうなのかが見える。
「今」を最善に生き切れば、過去も未来もすばらしいものになる。
「今・今・今」
「今」が大切なんだよ。と言われている気がします。
きのう頑張ったから、今日はちょっと一休み。
あしたから頑張るつもりだから、今はちょっと休憩しよう。と言っているうちに、「今」はどんどん怠惰な過去になり、怠け癖のついた未来が現れてくる。
真摯で、そして厳粛な言葉です。
ある美術館で、清澄な雰囲気を醸している壺に出会いました。何の変哲もない色と形の壺でしたが、その雰囲気に引き寄せられて近づいてみると、「河井寛次郎作」との銘が付いていました。
わたしたちの人生も、こんな空気を纏えるようになりたいものです。
「今」の姿勢がこのような空気を醸し出すのでしょう。
年頭にあたり、気持ちを引き締めて「今」を生きたいと決意を新たにしました。
2019年1月10日
気持ちよく晴れ渡った元日に、在籍生、卒業生の皆さんから心のこもったお年賀状を頂きました。
一生懸命書いてくれたであろう、かわいい年賀状や、
今年の抱負を書いてくれた年賀状、
近況を知らせてくれる年賀状、等々それぞれの思いが手に取るように感じられました。
みなさん、ありがとう。
小さいお子さまにとって「ハガキ」を出すことは、普段あまり経験のないことではないでしょうか。まして大人でも最近はメールが主体です。ですが年に一度でもこのような機会があることは、お子さまにとってとても意義あることだと思います。慣れないハガキを子どもに書かせるより、親が書いた方がよほど楽だと思います。敢えてお子さまに書かせるメリットは何でしょう?
子どもはこの経験において、日本の伝統を感じ、社会に繋がる実感を持てるのではないでしょうか。
一生懸命書いた賀状には、お子さまの一生懸命な姿が滲み出ています。年始の挨拶の気持ちが伝わってきます。
お正月には、初詣、お年始、七草粥、鏡開き、どんど焼き、成人の日の小豆粥等々多くの行事が詰まっています。
又一年を通じて、節分、桃の節句、端午の節句などいろんな行事があります。現在では省略されているものも多いですが、できることはお子さまとご一緒に参加して頂きたいと思います。このような経験を重ねることで、「日本のこころ」が世代を繋げていってくれることを願っています。
お正月はお年玉を頂く日、どんど焼きはお餅を食べる集まり。ではなく、それぞれの行事の意味を伝える機会となれば幸いです。
2019年4月1日
新しい学校、新しい学年、新しいクラスで学ぶ生徒さんたちの希望と不安の入り混じった息吹を感じる季節です。桜の花も七分咲きほどに一気にほころびました。
望み通りの環境に満足している人、そうでない人、それぞれでしょうが、決まったところが今の自分にとって最上の場所です。覚悟を決めて、今与えられた場を大切に、懸命に、最善を尽くして欲しいと思います。そして次のステップを定めて邁進しましょう。
春爛漫のこの季節は、そんな明るい未来を見据えて、突き進むにふさわしい空気が満ち満ちています。
英語の“Spring”も、「跳ねる・弾く・芽を出す」等々ワクワクした状況をあらわしています。