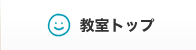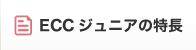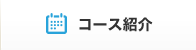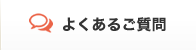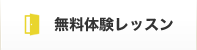「あづかれる宝にも似てあるときは吾子(わこ)な
がらかひな畏(おそ)れつつ抱(いだ)く」
いくら立派な教育論に基づいた教育を施しても、子どもの一挙手一投足に注意を払って育てても、子どもは教えられた通りには育ちません。だからと言って、子どものすべてに責任を感じることも不要です。子どもには、立派に育つ力が備わっているからです。
親が責任を持つべきは、「命にかかわること」及び「人の道を外しそうになった時」のみ。
それ以外の時は、思い切り愛して褒めて、喜んであげること。子どもと共に生きる喜びを全身で感じ幸せを満喫すること。
冒頭の皇后陛下のお歌のように、預かっている宝を大切に、また一つの人格として敬意を持ってお世話させていただく。というつもりで、親は子どもにどう育って欲しいのか、「親が理想とする姿」を常にやって見せ続けることが大切です。
日々の些細な失敗にくよくよ悩み続ける姿を見せ続けるのか、明るく前向きに子どもの存在を心から喜び子育てを楽しんでいる姿を見せ続けるのか。
気持ちを軽く、子どもと触れ合うことの幸せを満喫して欲しいと思います。
何事も立派に完璧にこなせるすてきなお母さまから、子育てのお悩みを相談されました。お友だちと仲良くでき、みんなに好かれ能力も高いかわいいお子さまなのに、何がお悩みなのか?
わたしから見ても、このお母さまは他のお子様たちへの接し方もとても自然ですばらしいといつも感心している方なのです。
「うちの子はHSPではないか、わたしの接し方が悪かったのではないか、厳しくしすぎたのでは?」と悩み続けていらっしゃったようです。
お子さまへの愛情が深く、教育熱心な方ほど悩まれるのですが、悩んでいる姿を見せ続けて、いいことがあるでしょうか?「自分なりに精一杯のことをした。」と思えたらあとは子どもに授かっている能力にお任せして、気持ちを軽くして、今ある幸せを大いに満喫すること、多少間違ったことがあっても、消しゴムで消すようにきれいに心から消して、明るく楽しく毎日を過ごすことを心がけることが大切では?とお伝えしました。
それでは気持ちが治まらないと思うときは、きちんと「どういうところが間違っていた」「あの時のこういうところが悪かったわ、ごめんね。」と伝えればそれでOK!
失敗も間違いもいくらでもやり直すことができるのです。