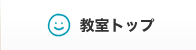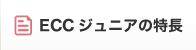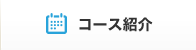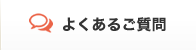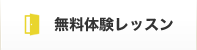2019年6月14日
今日は5年生6年生クラスに、ホームステイしているアメリカンの女の子が参加して発音チェックを手伝ってくれました。
特にみんなの気づきはrの音の違い。
英語の発音は息とアクセントが日本語より強い。
そのことを生の英語から感じるいい機会だった。彼女のアドバイス。
文法ができていても、発音がカタカナ発音だったり、アクセントが違ったり何より自信がなくて声が小さいと、聞き取りにくいとのこと。
ジモティーの話には説得力あるなぁ~。
新たに頑張る気持ちがムクムク沸いた今日のクラスでした。
2020年12月24日

寒くなってきましたね~。
講師は最近キノコ鍋にハマっています。エリンギ、まいたけ、ぶなしめじ…。色々なキノコ類を入れて、煮込んで食べるんです。腸の働きを活性化させて、体もあったまる。最高。
きのこ~の こ~のこ げんきのこ…♪
でもレッスンで時間がないときも。そんなときはパスタをよく食べます。パスタを茹でて、ソースを絡めて、手軽で簡単、美味しい。
た~らこ~ た~らこ~ たっぷり た~らこ~…♪
……なんだか懐かしいと言うか、久々に聴くメロディーではありませんか?
昔テレビのCMでよく流れていたので、覚えている方も多いのではと思います。とてもキャッチーで、耳に残る…謎の中毒性のある曲ですよね。
でも、このCM、結構前に放送されていたのに、なぜこんなにも簡単に思い出せるんでしょう。
『先週の水曜日の晩ごはん何食べた!?』って聞かれても、「えっと…」となるのに、もっと昔のこの曲はなぜこんなに簡単におもいだせるのでしょう。
覚えやすいメロディーだから?
映像にインパクトがあったから?
実は、これには脳の記憶のメカニズムが関係しているんです。
記憶には短期記憶と長期記憶があります。短期記憶とは、20秒以内の記憶のことを指し、長期記憶は20秒以上の記憶を言います。
そして、人がものを覚えると言うことは、この短期記憶を長期記憶に移すメカニズムのことを言います。
テレビCMは15秒、ラジオCMは20秒と言う規定があるそうです。CM自体は短期記憶にしかなりません。
ではどのようにして長期記憶に移すか。
それは、繰り返す(反復)と言う方法で実行されています。
テレビのコマーシャルは、だいたい15分~20分おきに入ります。1時間の番組なら3~4回繰り返してみることになります
こうして、反復することで人の長期記憶に入り込み、定着させる ”からくり” があるんです。
この作業は脳の”海馬”という場所で行われています。海馬は記憶の番人と言われています。覚えているか、忘れるかはこの海馬にかかっています。
海馬は一度だけしか来なかった情報は「さほど必要じゃないな…」と判断し、保持しようとしません。しかし、何回も何回も来る情報に対しては「これは必要な情報だな。」と判断して、保持しようとします。
つまり、何かを覚えるには、何度も何度も繰り返して、記憶の番人に顔を覚えてもらわなければなりません。
講師がいつも生徒に復習するように促すのには、こうした理由があります。英語に限らず、何かを学ぶ、覚えるときには反復することがとても大切なんです!
…まぁ、ただ反復すればいいというわけでもないんですけどね。その話はまた今度にしましょう。
では、最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
2021年1月18日
こんにちは!
遅ればせながら、今年もよろしくお願いいたします!
さて、今年一発目の話題は、新しい英語教育についてです。
文部科学省が挑戦的な発表をしてきましたね。来年度中学校の学習指導要領が大きく変わるそうです。
学校の教科書は4年に1度改訂があり、12年に1度大改革があります。2021年は大改革にあたるそうです。
そして、英語は特に大きく変わり、難易度が爆上げされます。簡単に取り上げると…
ア.4技能5領域に
聞くこと・読むこと・書くこと・話すこと(やり取り)・話すこと(発表)
イ.授業
原則、授業はすべて英語で行うことに
ウ.英文法
「仮定法」の基礎/「原形不定詞」/「現在完了進行形」/などを追加
エ.英単語
3年間で扱う英単語は1600~1800語に (現行1200語)
…だそうです。
ア、イ、ウも大変そうですが、注目すべきはエの英単語です。単語数が激増します。ECCの教材も新版から2倍の単語を一度に入れるシラバスになっています。小学校低学年でも、今までは進出単語は6語でしたが、来年度からは倍の12語に増えています。
…大丈夫なんですかね。覚えられるんですかね。むずいっすよね…。
ところで、去年の最後に記憶に関して少しお話ししました。
反復することで、脳の海馬に「これは必要な情報だ」と、認識させて覚える。繰り返して学習するしかないことをお話ししました。
…じゃ、増えた単語も、何回も反復すれば、覚えることができるんでしょうか。
まぁ、できるでしょうね(笑)。けど、1800語ですよ…。「青春=英語の暗記してました」になりますよね。
当たり前ですが、ただ反復練習すればいいわけではないんです。では、どうすればいいんでしょうか。さらっと学習しただけではすぐに忘れてしまいます。
長くなるので、今日はこの辺で終わりにします。
次回は、長期記憶の仕組みをうまく利用して、意味のある勉強にするために発寒4条教室が行っている工夫を紹介します。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
ほいでは。
2021年1月25日

第二回
どんも~。発寒4条教室です。
先週は、中学英語のレベルが改革されることをお話ししました。
今日はそのレベル爆上げに対して、どのように学習をしていくべきか、長期記憶の仕組みをうまく利用して、意味のある勉強にするために発寒4条教室が意識していることを紹介しようと思います。
まず、長期記憶についてもう少し考えてみましょう。
長期記憶にするには3つのステップがあります。
記銘 → 保持 → 想起
という段階で進んでいきます。
「記銘」とは、つまりは暗記する段階です。ここではたくさん発話したり書いたりして「覚える」と言う作業です。
「保持」とは、反復したものを保存しておく段階です。海馬にたくさん顔を見せて、記憶の部屋に入れてもらった状態です。
「想起」は、思い出すこと。記憶の部屋から出て必要な時にアウトプットする作業です。
これが長期記憶の仕組みです。この三つのステップができて初めて長期記憶となります。何回も、何回も、何回も…繰り返すだけでは「記銘」のステップにしかなりません。でも多くの方がこのステップで満足してしまっているんです。
では、もう少し具体的にこの三つのステップのポイントを見てみましょう。
まずは「記銘」ですね。
いわゆる暗記などの覚える作業です。ここでのポイントは、「意味ネットワークを作る」と言うところにあります。意味ネットワークとは、新しく覚えることと、既知の知識との関連性のことです。新しい単語を覚えるとき、自分が今まで覚えてきた単語とどんな関係があるかを考えます。意味ネットワークが繋がった時初めて覚えられるということです。
続いて「保持」です。
これはほぼ文字通り、記銘でインプットしたものを忘れずに保つことです。記憶の研究に、ドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスの発表した「エビングハウスの忘却曲線」があります。
細かい説明は省きますが、簡単に言うと人は時間が経つとどれくらいの量を忘れるかを調べた研究です(興味がある方はgoogleで検索してみてくださいね~)。人間は、時間が経ったら忘れる生き物です。忘れたところで、また覚え直して、保持していくしかないんです。
そして最後の「想起」。
これは、覚えたものを思い出すことを言います。つまりアウトプットですね。せっかく新ことを覚えたとしても、引き出しから出せなければ、「箪笥の肥やし」となってしまいます。思い出す練習も必要でなんです。
記銘 → 保持 → 想起
この3つのステップができて、初めて長期記憶、つまり「覚えている」ということになるんですね。
当教室では、このことを踏まえて教室活動を行なっています。特に、「意味ネットワーク」の構築には力を注いでいます。今までに勉強してきたことと、新しいことを生徒自身で結びつけられるように学習を進めています。宿題で覚えた文法、単語を、教室で覚えているか確認して、忘れていればもう一度覚え直して、アウトプットできるようにする。生徒にとっては、ストレスに感じるだろうし、容易いことではないでしょう。だけど、学生にプリント渡して、次のレッスンで丸つけて終了では、生徒のシャープペンシルの芯が減っただけで、何にもならないんですよ。
みんな大変だろうけど、長期記憶になるように意味ある勉強をしようね♪
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
ではまた~。
2021年2月3日
寒さが厳しい毎日、いかがお過ごしですか?
最近、『たけのこの里」のチョコレートの量が寂しくなった気がしてる発寒4条教室の講師ドリーです。
どうでもいいですね笑
たけのこは上にぐんぐん伸びていきます。生徒たちも、心身ともにぐんぐん上へ伸びていって欲しいものです。
そして、人間の成長には「チャレンジ」が必要だと思います。
試験もチャレンジのひとつでしょう。入試、資格試験、形は様々ですが、何らかの試験は今後の人生で必ず直面するチャレンジです。
英語の教室だと一番身近な試験は英検なんです。
英検®を受けることに賛否両論あるようですが、
私の友人の先生がおっしゃっていた大事にしたい事が私も同じだったので、そのまま転載させていただきます。
~以下友人先生のコメント~
「試験には意味はないとは思わなくて、準備をして実ったら次の挑戦の成功体験になるし、もし失敗してもそれをどう活かすかということを学んで次の成功体験に使えばいい。
試験はXデーがあるから底力が出たり自分と向き合ったりできる。
そうやって利用すればいい。
でも、大人が子供を評価したり、それによって順位付けしたりするために試験を使うのは違うと考えています。
試験は人生を決めない。成長に使う。」
私も、合格、不合格ではなく、そこに至るまでの過程が大切なだと思います。
英語に限らず、学校教育が大きく変化し、難易度が激化したり、早めの準備を呼びかける声があちらこちらから聞こえてきます。
このことに関して、親の方が敏感になりすぎている傾向があります。
子どもの学習に過干渉になってはいけないとわかっているけれどどうしても気になって口を出してしまう。
親ならあるあるなことです
が、残念ながらその子のためを思って、将来苦労しないようにとやればやるほど子どものやる気は下がります。
親の本当の思いが伝わり、子どもから相談したい相手に選んでもらえるような親になりたいものですね。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
コロナがまだまだ心配な世の中、皆さんお元気で。