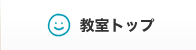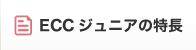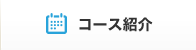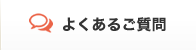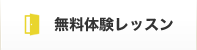2019年11月23日
1・2年生クラスで暗唱練習をしました。
暗唱については以前にも書きましたが、暗唱する絵本の内容をしっかりと理解していることが大切なのと、感情をこめて読む表現力をつけて欲しいと思っているので、まずは日本語で音読練習をします。
早速一度読んでもらうとみな上手に音読することができました。ただ最初から感情をこめた音読ができるわけではありません。表現力を着けた音読をするには何回も練習が必要ですが、何回も読んでねというだけだとみんな飽きて練習してくれません…。表現しながら読むということをするからこそ、うまくなるために何回も練習してくれるんだと思います。
でも表現をつけた音読ってどうするの?となりますよね。なので一度読んでもらった後、『先生が一回読んでみるから聞いててね』と言って読んでみました。ここぞとばかりに感情をこめて、物語に出てくる毛虫になりきって読んでみました(笑)少し大げさにする方が子どもたちにはわかりやすく、面白いと思ってくれるようです。読んでいるとみんなどんどん笑顔になって、『面白い、面白い』と言ってくれました。”表現をつけて読むと面白い”と感じてもらうという企みはなんとか上手くいったようです…(笑)
私が読み終わると早速『僕、もう一回読んでみる』との声が。役の声を変えたり、食べ物を見つける場面のところで大きな驚いた声を出してみたりと2回目の音読で早くも表現しようとしてくれました。
それを見ていた他の生徒も2回目の音読に挑戦していってくれました。
これから、もっともっと表現力が磨かれていくと思います。これからの練習が楽しみすぎて、今からニヤニヤしてしまいます。みんな頑張ろうね!
2019年11月24日
今日のPIクラスのレッスンで嬉しいことがありました。
スタンプチャレンジをしていると、一人の生徒が、『先生、ここ何回も練習してきたから、暗唱に挑戦してみていい?』と聞いてきました。嬉しいリクエストに『もちろん!やって、やって!』と答えました。
最後までしっかり暗唱出来た後の生徒の顔がとっても誇らしげな表情だったのが印象的でした。普段はどちらかというとおとなしい子で、あまり自分からこれをやってみたいということがなかったので、その自発的な挑戦に感動しました。
私がやりなさいといって挑戦するのと、自発的に挑戦するのとではその成長度合いが全く違います。やりなさいという強制では成長しません。
そして自発的に挑戦する生徒を見ると他の生徒も影響を受けます。今日もその後『私もやってみようかな』と、他の生徒も暗唱に挑戦してくれました。生徒が成長するのは生徒同士が刺激し合う時だと思います。いい影響をお互いに受けてどんどん成長していってもらえるようなクラスを作っていきたいと思います。
2019年12月2日
うちの息子は今ウルトラマンや仮面ライダーにはまっています。もう大好きで仕方ないという感じで、時間があれば本を眺めています。
ウルトラマンシリーズの人形もいくつかうちにあります。息子はその人形を家のあちこちに隠して見つけるという遊びにはまっています。
毎日、いっぱい人形を持ってきては『ママ、これ隠して』と言ってきます。
隠した後すぐに人形を探しに行けるわけではありません。”Are you ready?” と聞いて、”Yes!”と返事があれば探しに行けます。面白いのでついつい何回も”Are you ready?” “No!”のやり取りをしてしまいます(笑)
息子は英語でやり取りしている意識はありません。ただ人形を探しに行く合図としてのやり取りをしているだけですが、自分の目的を達するために言わなければならないとわかったのですぐに”Are you ready?”と聞くようになりました。
遊びの場は学びの場、息子を見ているとそう思います。
遊びが学びにつながる、そんなレッスンをしていきたいと思います。
2019年12月2日
忘れられない先生の3人目はアメリカ留学中の地学の先生、アルドリッジ先生です。
とても明るい先生で、いろんな生徒とグループを組ませてくれたり、ノートを取る時間を取ってくれたりと私がクラスに馴染めるよう手助けしてくれた先生でした。
地学のクラスはとてもユニークでした。教科書を読むことはほとんどなく、映像を見て意見を発表しあうという形式でした。学年の最終試験でも筆記試験などはありませんでした。その代わり一年間で学んだことを何でもいいから形にするというのが課せられた試験でした。準備期間は2、3週間だったと思います。
私は上流から下流までの川の流れの変化とその流れによってできる地形の変化を表現しようと決めました。大きなパネル板を買ってきて、そこにまず川を作り、窪みや岩や砂、木、草など細かいパーツを粘土で手作りして置いていきました。動物は折り紙で作りました。長さ2mほどの作品が出来上がった時には、『できた〜!』という達成感がありました。
学校にその作品を持って行った時、運んでいる最中に他の生徒や先生から、『すごいの作ったね』と何度も声をかけられたことは20年以上たった今でも忘れられない思い出です。
クラスで1名代表で学校の展示に作品を出せたのですが、クラスにはほかにもたくさん面白い作品を作った生徒がいたので、私のは選ばれないかもしれないなと思っていました。結果的には私の作品を飾ってもらえたんですが、先生にその理由を聞くと、『まずオリジナリティがあり創造的だから』と言われました。
アルドリッジ先生はとにかくいつもオリジナリティにこだわる先生でした。独自の物の見方、意見を喜ばれました。創造的でありなさいともよく言っていました。
独自性と創造性、どちらも今の時代に欠かせない資質だと思いますが、英語の教室ではどんな時でも受け入れてもらえると思ってもらえてはじめて生徒は独自性や創造性を発揮できるようになるんだと思います。アルドリッジ先生が私にそう感じさせてくれたように。そんな環境を提供していけるよう私にできることを精いっぱいやっていきます。
2019年12月2日
11月中旬から冬の懇談会が始まりました。
たくさんの保護者様に来ていただき、お話をさせてもらえてありがたいです。教室での様子、頑張っておられるところ、来年度のクラスのこと、学習方針などいろいろお話させていただいています。
保護者の皆様から、『先生のところやったら行くって子どもが言うんです。』と仰っていただくことが何度かあり、とても嬉しくまた身が引き締まる思いがしています。先生のとこなら行く、そう思ってもらえる環境をこれからも作っていけるよう頑張ります。
みんな、本当にいつもありがとう。