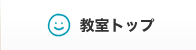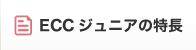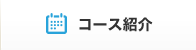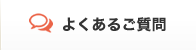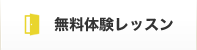2019年11月13日
今日のPFクラス(1・2・3年生クラス)ではdriveやstudyといった動作動詞を学びました。動詞を練習する時は実際にその行動をつけて練習するようにしています。その方がみんなが断然楽しそうだからです(笑)
今日もJump! Drive! Sleep! Laugh!など次々に動作していきました。高く飛ぼうとする生徒、何度もジャンプする生徒などJump!一つでも生徒によって動作の仕方が違います。そこがまた面白いところです。どんどんスピードを上げていったので、軽い運動になりました(笑)
何度かやっていると、『俺が言いたい!』と言う生徒がでてきます。そんな時はどんどんやってもらっています。やってみるとうまく言えない時もありますが、そんなことは気にしないで大丈夫!みんなの前で習いたての英語を使ってみる体験にまさるものはありません。『やりたい!』という生徒さんを見るたびに頼もしく感じます。
これまでの復習を兼ねて動作動詞連続50!なんていうプチ体操を作ったら面白そう…(笑)早速やってみたいと思います!
2019年11月16日
英語学習には動機付けが必要です。特に幼児から小学生まではこの動機付けをいかにするかがカギになります。中間北教室では海外の同年代の学生との交流を動機付けの機会にしてほしいと思い、交流プログラムを行っています。
海外の学生に現地のことを教えてもらう、反対に日本のことや自分の身の回りのことについて教えてあげるという相互交流を目指して、フラットスタンレープロジェクトを活用しています。
フラットスタンレープロジェクトはアメリカの絵本
『フラット・スタンレー』を基にしてできたプログラムです。各自がそれぞれのフラットスタンレーを作り、海外に送りだします。自分のかわりに世界各地を見て回りいろんな経験をしてきてもらうというとても面白いプログラムです。
中間北教室にはこの一年弱の間だけでもアメリカ(ハワイ州、モンタナ州)、オーストラリア、アイルランドからフラットスタンレーがやってきました。イギリスからもやってくる予定になっています。
まず届いたフラットスタンレーをお世話してくれる生徒を募ります。決まった生徒は自分が紹介したいと思う文化や食事、場所を考え、それにそってフラットスタンレーと一緒に写真を撮ります。写真の準備が終わるとそれを英語で説明していき、お手紙をつけて相手に送り返します。
オーストラリアやアイルランドの学校とはスタンレーの交換もしたので、こちらからも生徒オリジナルのスタンレーを送りました。海外から届いた自分あての手紙や写真にとっても嬉しそうにしていました。
これからもいろいろな方法を活用して海外との交流プログラムを進めていきたいなと思っています。
■サブ画像:
住んでいる町の近郊について紹介。
芦屋の桜と命の旅博物館を紹介しました。
かわいいキャラ弁を紹介したいとパチリ。
キャラ弁は日本独自のものなので海外の方には興味深かったと思います。
お母様にもご協力いただきありがとうございました。
大好きなキャラクターについて頑張って説明しました。
手紙を書く用紙も各自で工夫します。
この時はオリガミに写真を貼り、裏に説明を書きました。
オーストラリアから届いた手紙と写真にご満悦。
届いた手紙を一生懸命読んでいました。
2019年11月16日
好きなものや好きでないものを伝えるI like apples.やI don’t like snakes.などは最初に学習する表現の一つだと思います。
これにあと一歩追加したいなと思い、I like animals, especially dogs!やI like apples but I don’t like apple pie.のように発表する練習をしました。面白い内容がどんどんでてきて笑いが止まりませんでした。
やっているうちに『I don’t like〜.やったらどうなるの?』という声が生徒からでてきました。みんなでどうすればいいかなと確認すると、すぐに”I don’t like chocolate but I like chocolate ice cream.”や”I don’t like vegetables, especially green peppers.”などばっちり文を作れるようになりました。
逆接云々の話は全くいりません。生徒の適応力は素晴らしいです。これはまだ難しいかもとこちらがリミットをかけてはいけませんね。発話の幅を広げられるレッスンを心がけていきます。
2019年11月21日
PFクラス(小学校1・2年生クラス)ではここしばらくwhereを使ってものがどこにあるかを質問したりそれに答える練習をしていました。
クマ形の消しゴムを使って、”Where’s my bear? Where’s my bear? On, in, under? On the box? In the Box? Under the box? Where?”とチャンツにして質問の言い方や答え方を練習しました。最初は”On the box”や”Under the box.”など質問に答えるだけでしたが、数回やると、『俺がやる!』『次、わたし〜!』と相変わらずの積極性を見せてくれました。
先生→生徒という質問の方向を生徒⇔生徒とお互いに質問にしあえるようにすると活動に活気がでてきますし、より楽しんで活動に参加してくれます。
今日はまとめの日だったこともあり、whereを使うアクティビティシートを行いました。今回も何をするのかは一切言わず渡しました。1年生は『何かわからん!』となっていましたが、2年生はシートをジッと見てそれぞれの動物の横にblueやgreenといった色を表す言葉が入っていることに気づきました。そして1年生に『ここにgreenって書いてるからクマをgreenで塗るんよ』と教えてあげていました。色を塗るということがわかった1年生はそれぞれの英語が何色を指しているのかを一生懸命考え始めました。2年生は色の単語がもう読めるので余裕でどんどんすすめていきます。1年生はそんな2年生を見て頑張ろうと思ったようで、『先生、これpやからpinkよね』などわかるところからなんとかしようと頑張っていました。どうしてもわからん!となった単語だけアルファベットの音をヒントに出すとすぐに何色を指しているのかがわかり皆時間内に色塗りが終わりました。
色塗りが終わった後に2枚目のシートを渡しました。今度は1年生も2年生もすぐにやることがわかったようで、動物とその動物がいた場所を線で結んでいきました。いつもとはまた違った活動で楽しんでもらえたようです。
目標言語が定着するようこれからもさまざまなアプローチからレッスンをしていきたいなと思います。
低学年のうちから無理のない範囲で単語の読みに触れていきます。
単語が1つでも読めると大きな自信がうまれます。
それぞれの動物がいた場所をon, in, underを使って発表します。
2019年11月21日
忘れられない先生の2人目はヘッド先生です。
ヘッド先生が私に教えてくれたことは私には私の意見/考えがあるということです。
ヘッド先生はことあるごとに、『キミコにはキミコの意見があるはずだ。』と言っていました。
日本の学校も今はだいぶと変わったと思いますが、私の学生時代はどちらかというと自分の意見を表明することは難しいことでした。
ヘッド先生の『キミコにはキミコの意見があっていいんだ。意見を言うことを恐れてはいけないよ。』という教えはカルチャー―ショック以上のものがありました。
クラスメイトの意見をなぞって答えるのではなく、自分がどう思うかを伝えようと思うと、その対象について考える必要があります。意見をまとめ人に伝わるようにするにはどうすればいいかということも考えねばなりません。考えるということは学びそのものだと思いました。
自分の考えを伝えるには勇気がいることもありますね。その意見を言っても大丈夫だろうか?と心配することもあるかと思います。受け入れてもらえるという安心感がないと難しいこともあると思います。
ですので中間北教室では、
①自分はどう思うかを考えること
②自分と他者の考えの同じところ、違うところを知ること
③多様な意見を受け入れる寛容さと受け入れられる安心感を得ること
がとても大切だと考えています。
ヘッド先生の『君には君の意見があっていいんだ。自分の意見を言うことを心配しなくていい。』という言葉を生徒のみんなにも伝えていきたいなと思います。