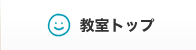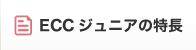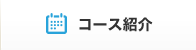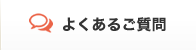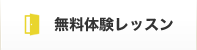そんな中、私たちはどのような学力を育むことで、より良い社会を切り開き、より充実した人生を開いていけばよいのか・・・?という事が、この「学習指導要領改訂」の中核と言えるものなのかと思います。
2)大学入試変革(英語「話す」力を採点導入)は、「大学受験をするしない」に関わらず、小さいうちからやらねばならない事を明確にする!
「大学の入試が大きく変わる」という事は、教育過程そのものが大きく変わるという事です。大学を受験するや否や・・と、そのようなことではなくて、すべての子供たちの教育がこの大学入試改革に影響されるという事なのです。
今回、今まで「ガラパゴス入試」と揶揄されてきていた「話すことはできない英語指導学習要領」にやっと風穴があき「実用英語検定試験」などの外部試験によって「話す力」が4分の1の配点で評価・採点されることとなりました。
日常的に英語を使う環境にない私達には、やはり小さいうちから、意識的に「聞いて覚える」->「話すチャンスを多く作って定着させる」という事を繰り返し、英語を日常とすることが一番の早道で確かな方法であると私は考えております。
私が、「発表会」や「イベント」等を可能な限り多く繰り返す理由はここにあります。
*英語は十分に英語を覚えてから話す・・・と言うように考えていては、絶対に話せるようにはなりません。日常的な言葉を、できるだけ様々な英語環境場面で、多く使っていくことが効果的と考えます。
3)今、新学習要領変更内容から見て、幼稚園・小学生・中学生の子供たちに必要なことは何か?
新学習指導要領では、英語だけでなく、数学も国語もその「学習内容が約1.2倍(それ以上?と思います)」に増えていきます。
これは、今のAIにはできない「読解力」を充実させ「文章から多くのものを得る力」を育てようとしている結果ではないかと思います。つまり、「自から学ぶ」ことを大切にしようと小・中学校の新指導要領には「記憶し理解していることをどう使うか?」という「思考力・判断力・表現力を育てる」という項目が新たにはっきりと明記されています。
さて、
4)覚えることが増え、それらの知識を使って、自ら表現することが期待されている子供達。
どのように限られた時間を有効に利用すればよいのでしょうか?
私は、以下のように考えます。
お子さんたちの学習の様子を見ていると、「同じことを聞いても同じ文面を見ても、理解できるスピードが全く違う」という事があります。
中学生ではほぼ皆、テスト前に必要な箇所を一生懸命覚えますが「テストの点に差が出てくるのはなぜでしょうか?
それは、やはり「覚えた内容の背景を総合的に読み取り理解をしているかどうか」という事に直結します。
小・中学生に行われた「全国読解力テスト」では、「3人に1人は、AIと同じように読解力が弱かった」そうです。お子様はいかがでしょうか?
文章を早く正確に読めるようになるためには、何より、「多くの文章を読む事がとても大切」です。
小さいうちから「絵本の読み聞かせ」等、本に親しむ楽しさを充分に味あわせてあげてください。
読書の習慣を小さいうちから付けることは、何より「沢山の情報を読み取り、更に早く情報を処理する能力を育て、学力や創造力の底上げにつながる」と確信します。
また、「対」人工知能と言うだけでなく、「同じ文章から多くの物を得る力があればそれだけでも人生は豊かになる」のではないでしょうか!?
小説でも好きなジャンルの内容でも「本好きな子に育てる」ことが、今後の課題の一つになる・・・と言えると私は思っています。
以上キーワード「話せる英語」と「読解力強化」による学力の充実。今回は、このような内容でお話させていただきました。(と言うつもりでした(^^:)
今後とも、お子様は勿論、ご父兄様共々に前進できる塾として進化させていただいたいと願っています。
*最後までお読みいただきありがとうございました。